抑制性T細胞の研究で大阪大学の坂口志文教授がノーベル賞受賞されました。
この研究は以前から知られていて、やっとノーベル賞取ったか!という印象です。
制御性T細胞とは何?と思われてる方も多いと思いますので今回はTreg細胞(制御性T細胞:Regulatory T cell)の働きをわかりやすくまとめます。
Treg細胞とは?
Treg細胞(制御性T細胞)は、免疫反応を抑制してバランスを保つ役割を持つTリンパ球の一種です。
主に自己免疫の暴走を防ぎ、過剰な炎症反応を抑える「ブレーキ役」として働きます。
主な特徴
項目 内容
起源 ナイーブT細胞(未分化のT細胞)から分化
代表的なマーカー CD4⁺, CD25⁺, FOXP3⁺
主な分化因子 TGF-β, IL-2
主な分布 末梢リンパ組織、腸管、胸腺など
Treg細胞の主な働き
- 自己免疫反応の抑制
-
• 自己反応性T細胞(自分の組織を攻撃するT細胞)を抑え、自己免疫疾患を防ぐ。
• FOXP3遺伝子が欠損すると自己免疫疾患が発症する(例:IPEX症候群)。 - 炎症反応の制御
-
• 感染や損傷後の過剰な免疫反応を抑えて、炎症を鎮める。
• サイトカイン(IL-10, TGF-βなど)を放出して、他の免疫細胞の活性を抑える。 - アレルギーや慢性炎症の調整
-
• アレルギー反応を起こすTh2細胞や炎症性Th17細胞を抑制。
• Tregが減少すると、アトピーや喘息、炎症性腸疾患などの悪化に関与。 - 移植免疫の制御
-
• 臓器移植後の拒絶反応を抑制。
• そのため、Treg細胞を増やす療法が免疫寛容(トレランス)誘導として研究されている。 - がん免疫との関係
-
- がん組織内ではTregが過剰に働き、免疫攻撃を抑えることがある。
- 結果として、がん細胞が免疫の目を逃れて増殖しやすくなる。
Treg細胞を活性化・抑制する栄養・生活習慣
活性化(=免疫のバランスを整える・炎症を鎮める)
Treg細胞を増やしたり働きを高める要因は以下の通りです
栄養・食事要因
栄養・食材 作用・メカニズム
ビタミンD Treg分化を促進(FOXP3の発現を誘導)。欠乏で自己免疫リスク増。魚・卵・日光。
オメガ3脂肪酸(EPA/DHA) 炎症性サイトカインを抑制し、Treg活性を高める。青魚、亜麻仁油。
食物繊維(特に発酵性繊維) 腸内で短鎖脂肪酸(特に酪酸)を産生 → Treg誘導。野菜・豆・オート麦。
ポリフェノール(緑茶・カカオ・ブルーベリー) 抗酸化・抗炎症作用+Treg誘導。
亜鉛・セレン FOXP3転写の安定化や免疫恒常性維持に必須。欠乏でTreg減少。
生活習慣要因
習慣 影響
十分な睡眠 メラトニンやコルチゾールのリズムが整うとTreg機能が安定。
適度な運動 軽〜中強度の運動でTreg増加(慢性炎症抑制)。過剰運動は逆効果。
ストレス管理 慢性ストレスや高コルチゾール状態はTreg減少の要因。瞑想や呼吸法が有効。
腸内環境の改善 後述するように、腸内代謝物(酪酸など)がTreg活性を直接調整。
抑制(=Tregが減る、働きが弱まる要因)
要因 内容
加工食品・高脂肪・高糖質食 腸内環境の悪化・炎症性サイトカイン増加によりTreg減少。
慢性ストレス コルチゾール上昇により免疫バランスがTh1/Th17優位に傾く。
睡眠不足 自律神経とホルモンバランスの乱れで免疫過敏状態に。
喫煙・アルコール過多 酸化ストレスと腸内毒性によってTregが減少。
腸内環境とTreg細胞の関係
腸は免疫細胞の約7割が存在する最大の免疫器官で、Treg細胞とも非常に深い関係があります。
腸内細菌が作る「短鎖脂肪酸(SCFA)」
特に 酪酸(butyrate) がTreg誘導のカギ。
酪酸は大腸で発酵性食物繊維(イヌリン、オリゴ糖、レジスタントスターチなど)から作られる。
酪酸はFOXP3遺伝子発現を促進ナイーブT細胞をTregへ誘導
腸のバリア機能を強化という多重の免疫調整効果を持ちます!
代表的なTreg誘導菌
菌種 特徴
Clostridium cluster IV, XIVa 酪酸産生菌。腸内Tregを増やす代表格。
Faecalibacterium prausnitzii 炎症抑制性の腸内細菌。潰瘍性大腸炎で減少。
Bifidobacterium(ビフィズス菌) 乳酸+酢酸産生 → 酪酸菌をサポート。
Lactobacillus(乳酸菌) 腸上皮バリアを強化し、Treg増加を間接的に支援。
腸内環境と全身Tregの関係
腸で誘導されたTregは血中に移行し、全身の炎症抑制・自己免疫抑制・神経免疫調整にも関与する。そのため、腸内環境を整えることは単なる消化ではなく、免疫の恒常性=Tregの健全性につながります!
Treg細胞活性化食事モデル
Treg細胞を活性化し、炎症を抑えつつ免疫のバランスを整えるには、「地中海式+和食」 をベースにすると最も効果的です。
1日の基本構成(例)
食事 主なポイント
朝食 腸内細菌のエサ+抗炎症栄養を入れる
昼食 タンパク質とオメガ3で免疫細胞の材料補給
夕食 発酵食品+食物繊維で腸とTregを整える
朝食例:腸内Tregを起こす
オートミール(βグルカン・レジスタントスターチ)
ヨーグルト+オリゴ糖 or はちみつ(乳酸菌+エサ)
キウイやブルーベリー(ポリフェノール)
緑茶(EGCGがTreg活性をサポート)
発酵性繊維 × ポリフェノールで酪酸菌が活動開始。
昼食例:免疫バランスを養う
鯖・鮭・イワシなどの焼き魚(EPA/DHA)
玄米 or 雑穀(食物繊維+ミネラル)
具沢山味噌汁(発酵食品+野菜)
サラダ+オリーブオイルドレッシング(抗炎症脂質)
オメガ3と発酵食品でTreg分化を促進。
夕食例:腸でTregを増やす
納豆・キムチ・ぬか漬け(プロバイオティクス)
豆腐・青菜・きのこ類(マグネシウム・繊維)
さつまいも・ごぼう・長芋(発酵性繊維)
味噌汁+ワカメ(発酵×ミネラル補給)
夜の腸内環境を整え、睡眠中の免疫修復を助ける。
腸内でTreg誘導を狙うサプリ
腸内のTreg活性を高めるには、「酪酸・乳酸菌・食物繊維」 の3本柱を組み合わせるのが基本です。
酪酸・短鎖脂肪酸系
目的:ナイーブT細胞→Tregへの分化誘導
成分 ポイント
酪酸(Butyrate) 直接Treg誘導を促す。腸管のFOXP3発現を増加。
酪酸菌(Clostridium butyricum) 代表的Treg誘導菌。例:ミヤリサン、MIYARISAN®製品。
レジスタントスターチ系プレバイオティクス 酪酸菌のエサ。イヌリン・アカシアファイバーなどと併用が◎。
おすすめ組み合わせ
「酪酸菌+イヌリン」=Treg誘導に最も効果的なペア。
プロバイオティクス(生きた菌)
目的:腸内炎症を抑え、免疫恒常性を整える
菌種 主な特徴
Bifidobacterium breve / longum 炎症抑制型でTregを増やす報告多数。
Lactobacillus casei / plantarum 腸上皮のバリア機能を強化。Treg誘導を補助。
Faecalibacterium prausnitzii 次世代プロバイオティクス。酪酸産生性が高い(まだ医療レベル)。
選び方のコツ:
• 複数菌株配合タイプ(3〜10種類)を選ぶ
• 腸溶性カプセル or 常温安定型が望ましい
• 継続2〜3週間で効果判定を
プレバイオティクス(腸内菌のエサ)
目的:Treg誘導菌を育てる
成分 特徴
イヌリン(チコリ根由来) 酪酸産生を促進。最もエビデンスが多い。
ガラクトオリゴ糖 ビフィズス菌を増やす。
アカシア食物繊維 マイルドでガスが出にくい。
💡摂取タイミング:
食後または就寝前(腸がリラックスしている時)に摂ると効果的。
補助栄養サポート
サプリ 働き
ビタミンD3 FOXP3発現↑、自己免疫制御。1000〜2000IU/日が目安。
オメガ3(EPA/DHA) 炎症性サイトカインを抑制し、Treg活性化を後押し。
マグネシウム 副交感神経の安定・腸運動サポート。
では自分のTreg細胞の状態を知るには?
簡単な方法は血液検査から推測するです!
Treg細胞そのものは末梢血単核球(PBMC)を分離してフローサイトメトリー(CD4⁺CD25⁺FOXP3⁺)で測定するのが直接法ですが、
一般的な健診や臨床検査では測定されません。
なので日常の血液検査では
Tregが活発か/減っているかを“間接指標”で推定
する形になります。
炎症と免疫バランス系の指標
項目 理想的な傾向(Tregが安定している時) 解釈ポイント
CRP(C反応性蛋白) 低値(0.03mg/dL以下) 慢性炎症が少ない。Tregが炎症を抑えている。
白血球分画(リンパ球比率) 30〜40%前後 炎症やストレスが強いと好中球↑・リンパ球↓。Tregも減少傾向。
好酸球比率 正常範囲(1〜5%) アレルギー反応があるとTh2優位→Treg機能低下。
血清IgE 正常範囲(〜170 IU/mL) アレルギー性炎症の指標。Treg低下で上昇しやすい。
サイトカイン(IL-10, TGF-β) やや高めが望ましい Tregが分泌する抗炎症性サイトカイン。※一般検査では測定困難。
自律神経・ストレス関連(Treg機能に影響)
項目 意味・関連
コルチゾール(血中・唾液) 慢性上昇でTreg抑制。ストレス過多を示す。
DHEA-S コルチゾールとのバランスが重要。DHEA低下は免疫老化・Treg減少傾向。
副交感神経優位時のHRV(心拍変動) 高値ほどTreg活性と関連(研究報告あり)。
腸内環境と関連する代謝・炎症マーカー
項目 解釈
AST/GOT・ALT/GPT 腸肝軸の炎症があると上昇。腸内毒素による慢性炎症→Treg低下。
γ-GTP アルコール・脂肪肝由来の炎症指標。高値はTreg機能低下傾向。
血清フェリチン 過剰(150ng/mL以上)は炎症マーカー。慢性炎症状態を示唆。
LDL-C / HDL-C比 高比率(>2.5)では炎症性サイトカイン優位。
HbA1c・空腹時血糖 高値は腸内炎症と免疫バランス崩壊に関与。Treg減少傾向。
免疫の過敏・自己免疫傾向を示す項目
項目 Treg低下と関連しやすい状態
抗核抗体(ANA) 陽性時は自己免疫反応が起こっている。Tregの機能低下を示唆。
免疫グロブリンIgG・IgA・IgM IgGやIgAが慢性的に高いと自己免疫活性化傾向。
Th1/Th2バランス(研究機関のみ) Th1/Th2比の乱れ=Treg調整機能の低下。
栄養・ホルモン系マーカー(Treg支援)
項目 望ましい傾向 理由
ビタミンD(25-OH-D) 30〜50ng/mL FOXP3発現とTreg分化を促進。欠乏は自己免疫リスク。
亜鉛(Zn) 80〜130μg/dL Tregの転写安定・抗酸化。
マグネシウム 正常上限付近 副交感神経安定・免疫調整。
EPA/DHA比(オメガ3指数) 高値(>4%) 炎症抑制とTreg機能維持。
Treg低下を疑う「血液データのパターン例」
傾向 可能性
CRPやフェリチンがやや高い(0.2〜0.5) 慢性炎症・腸内リーキーガット
IgEや好酸球↑ アレルギー・Th2優位
DHEA低下+コルチゾール高 慢性ストレスでTreg抑制
ビタミンD低値+Zn低値 免疫調整力の低下
HDL低・LDL高・γGTP高 腸肝軸炎症・Treg減少
以上Treg細胞についてでした!
みなさんに取っては特別な対策ではなく、日常的に気をつけてある事が多いのではと思います!
身体の中、代謝を中心にお伝えしましたが、当然ながら軸や向心力の狂いもTreg細胞に間接的に影響を及ぼします!
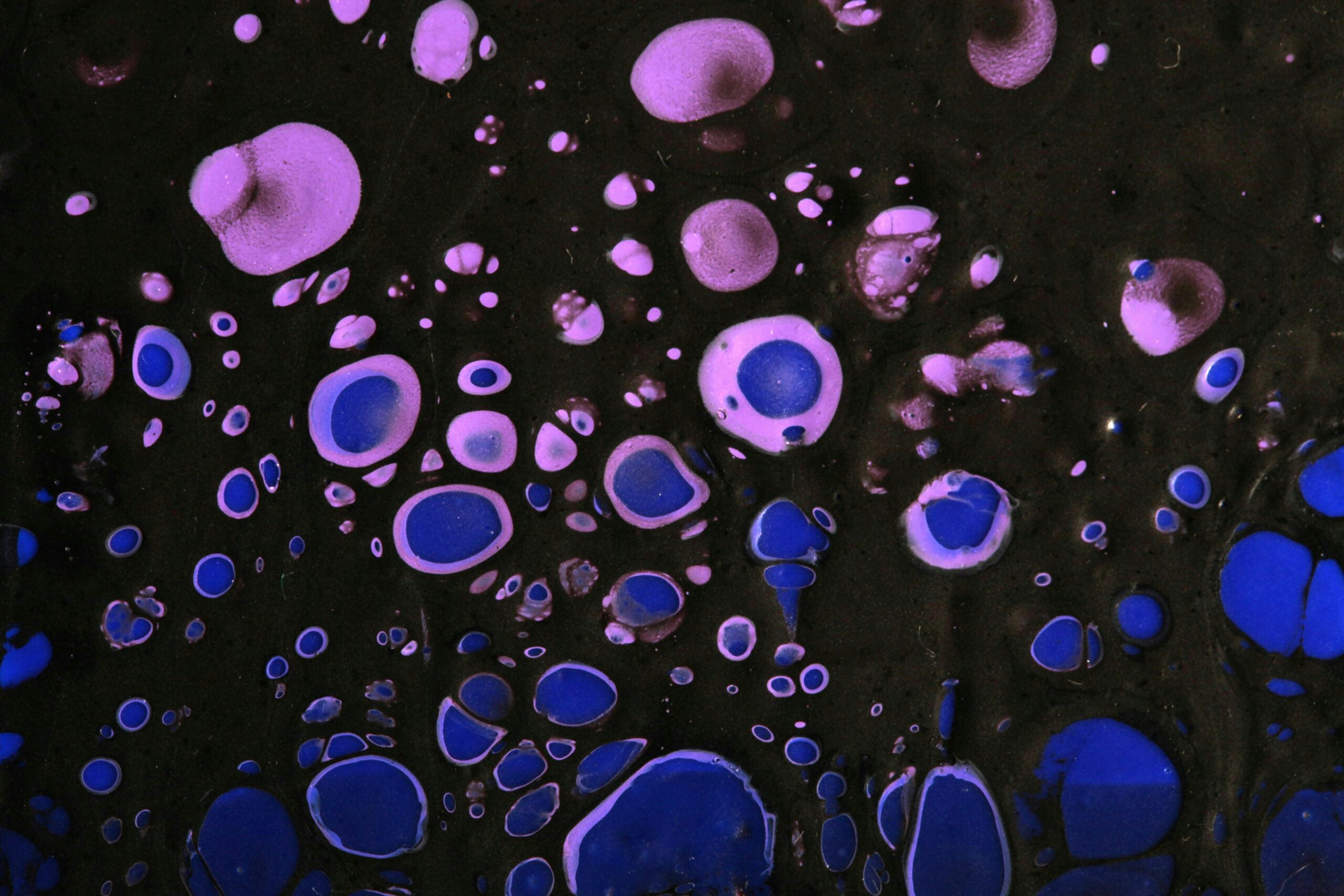




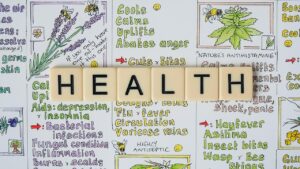



コメント