「ステロイド使用によってアラキドン酸カスケードが止まることの弊害」はたしかに存在しますが、工夫次第で軽減できる可能性があります。
アラキドン酸カスケードとは?
アラキドン酸(AA)は、細胞膜のリン脂質から遊離されて、
• COX経路 → プロスタグランジン(PGE)など(炎症、修復)
• LOX経路 → ロイコトリエンなど(免疫応答)
• リポキシンやレゾルビン → 抗炎症・修復
といった多様な生理活性物質に変換される重要な生体防御ルートです。
ステロイドがどう影響するか
• ステロイドはリン脂質→アラキドン酸を切り出すホスホリパーゼA₂(PLA₂)を抑制します。
• これにより、炎症性メディエーターの過剰産生が抑えられる反面、「炎症の終息」や「修復の信号」も止まってしまうリスクがあります。
ステロイド使用時の弊害の一例
• 組織の修復遅延
• 感染症への感受性上昇
• 粘膜バリアの弱化
• 慢性疲労、神経過敏
• 免疫バランスの偏り(Th1/Th2シフト)
副作用を軽減するセルフケア(分子栄養学+統合的視点)
1. オメガ3脂肪酸(EPA/DHA)を積極的に補う
炎症を抑える「SPM(スペシャライズド・プロレゾルビン・メディエーター)」に変換される
レゾルビン、プロテクチンは強力な抗炎症物質
• サーモン、いわし、アマニ油
• DHAサプリ(必要なら)
2. ビタミンC・E・グルタチオンなどの抗酸化栄養素
細胞膜の酸化ストレスを軽減し、PLA₂抑制の影響を和らげる
• ビタミンC:修復や免疫バランス調整にも重要
• NAC(N-アセチルシステイン)もグルタチオン前駆体として有効
3. 良質なタンパク質と必須脂肪酸のバランス
細胞膜を構成する栄養基盤を整える
• 卵、魚、良質な植物油
• アラキドン酸は過剰摂取でなくても、バランスと代謝力がカギ
4.マグネシウム・ビタミンB群(特にB6、B5)
炎症収束や神経系のサポートに役立つ
5. 腸内環境の強化(免疫と炎症の源)
発酵食品、プレバイオティクス、グルタミンなど
ステロイドで荒れた腸内細菌の回復を意識
ステロイドを使用してなくても細胞膜が酸化すると同じような事が起きます。
またビタミンB群の代謝が滞るため
- ステロイドはビタミンB群を消耗する
とくに影響を受けやすいのが
ビタミン 主な役割 ステロイドの影響
B6(ピリドキシン) メチレーション・神経伝達・ホモシステイン代謝 利用効率を下げる・肝臓負荷で失いやすい
B2(リボフラビン) FAD酵素・メチル基の活性化 酵素活性低下により不足しやすい
B12(メチルコバラミン) メチオニン合成、神経修復 胃腸障害→吸収不良になりやすい
葉酸(MTHF) DNA合成・メチル供与体の基盤 解毒力低下→相対的に不足しやすい
B群の欠乏症状以外に
ホモシステイン代謝が滞り、心血管イベントのリスクが上がったり
メチオニン合成が低下し、タンパク質の合成も低下してしまいます。
ビタミンB群不足が引き起こすメチレーションの乱れ
• ホモシステインが処理できなくなる → 血管・神経・ホルモンに負担
• 神経伝達物質(セロトニン・ドーパミン)合成の偏り
• 遺伝子のスイッチ(DNAメチル化)が狂う
• PMS・不眠・うつ・解毒不良・慢性疲労などの症状
メチレーション異常
「高メチレーション(過メチル化/Overmethylation)」とは、体内でのメチル基(-CH₃)の付加が過剰になっている状態を指します。
メチレーションは、遺伝子のスイッチ、神経伝達物質のバランス、解毒、エネルギー産生など多岐にわたって関わる重要な反応ですが、それが過剰になっても不調を招くことがあります。
高メチレーションとは?
• メチル基が「過剰に供給されている」状態
• 特に「SAMe(S-アデノシルメチオニン)>ホモシステインやSAH」のバランスが崩れていると、過メチル化に傾きます
• 葉酸・B12・メチオニン・コリンなどを過剰摂取した際に起こりやすいことも
高メチレーションの可能性がある症状
心身の状態 内容
✦ 不安感・神経過敏 刺激に過剰に反応する、イライラ、強迫的思考など
✦ 多動・過集中 落ち着かない、睡眠の質が悪い、夜型傾向
✦ 過眠 or 日中の眠気 エネルギーが過剰に使われて疲れやすい
✦ ドーパミン・セロトニン過剰傾向 一時的に気分が高揚→その後どっと落ちる
✦ アレルギー・炎症症状 免疫バランスが崩れやすく、皮膚炎や鼻炎などが出やすい
✦ 鬱っぽさ、燃え尽き感 高メチル状態が続くと逆に低下へ
高メチレーションになりやすい背景
• 葉酸やB12をサプリで多く摂っている
• メチオニン・SAMe・コリン系のサプリを使用中
• 遺伝的に「COMT酵素が低活性(神経伝達物質を分解しづらい)」
• ストレス耐性が低く、HPA軸が過敏に反応している
• 鉄や銅などのミネラルバランスが崩れている
(「HPA軸」とは、視床下部-下垂体-副腎軸(Hypothalamic–Pituitary–Adrenal axis)の略で、ストレス応答やホルモン調節の中枢的なシステムを指します。人体の内分泌系と神経系が連携して働く重要な経路であり、特に「ストレスホルモン」として知られるコルチゾールの分泌をコントロールします。
HPA軸の構成と働き
- 視床下部(Hypothalamus)
• 脳の一部。
• ストレスや昼夜のリズム、感情、血糖値の変化などに反応。
• CRH(コルチコトロピン放出ホルモン)を分泌。
⬇
- 下垂体前葉(Pituitary gland)
• CRHの刺激を受けて、ACTH(副腎皮質刺激ホルモン)を分泌。
⬇
- 副腎皮質(Adrenal cortex)
• ACTHの刺激により、コルチゾール(Cortisol)を分泌。
コルチゾールの役割
• 血糖値の上昇(グルコース生成の促進)
• 免疫抑制(炎症反応の制御)
• 血圧維持
• ストレスへの生理的対応(戦うか逃げるか反応)
➡ 一定量は必要だが、慢性的に高いと健康に悪影響(例:免疫低下、うつ、不眠、高血圧など)
フィードバック制御
• コルチゾールが増えると、視床下部と下垂体に「もう十分」と知らせてCRHとACTHの分泌を抑制。
• このネガティブ・フィードバックにより、ホルモンバランスが維持される。
🧪 関連疾患とHPA軸の異常
状態・疾患名 特徴
慢性ストレス コルチゾール過剰、HPA軸の疲弊(適応障害、バーンアウトなど)
クッシング症候群 コルチゾール過剰(副腎腫瘍など)
アジソン病 コルチゾール不足(副腎不全)
うつ病・PTSD HPA軸の調整障害が関与していると考えられる
対処・整え方のヒント
- メチル供与体の過剰摂取を控える
• 葉酸やメチルB12、メチオニン、SAMeを一時的に減らす - ナイアシン(B3)を使う
• メチル基を消費し、過メチル状態を穏やかにするとされます(少量から開始) - 副交感神経を高める生活習慣
• 深呼吸、温浴、自然との接触など - 銅・亜鉛・鉄のバランスを見直す
• 特に銅過剰は高メチル傾向に関連することも
もし心当たりがある場合や、B群サプリの使用中に不調が出た場合など、過メチル化との関連を一度見直してみるのもセルフケアの鍵になります。
《メチレーションタイプ簡易チェック》
✅ メチレーションのバランスを見極めるためのチェックリスト
いくつかの質問に「はい」「いいえ」で答えてみてください。
まとめて「はい、いいえ、はい」などでもOKです。
🌟 A. 過メチレーション傾向(高メチル)
- サプリで葉酸、B12、メチオニン、SAMeを摂取している
- 不安や焦燥感が強く、思考が止まらないときがある
- 感覚が過敏で、音・光・においなどに疲れやすい
- 過集中、または過活動になってしまうことがある
- 興奮のあと、どっと疲れる・気分の波が大きい
- PMSがひどい、不眠気味で夜に頭が冴える
- 銅やヒスタミンに過敏に反応しやすい
🌿 B. 低メチレーション傾向(低メチル)
- 集中力が続かず、物忘れが増えた
- いつも疲れていて、朝起きるのがつらい
- 落ち込みやすく、気力がわきづらい
- 肌荒れ、髪のパサつき、爪が割れやすい
- 解毒力が弱く、においや薬に敏感
- 口内炎・口角炎が出やすい
- ホモシステインが高いと言われたことがある
🍃 結果の読み方
• Aの「はい」が多い場合 → 過メチレーション(高メチル)傾向の可能性
• Bの「はい」が多い場合 → 低メチレーション(低メチル)傾向の可能性
• 両方当てはまる → メチレーションの波が大きい、または調整力が弱っている可能性
「低メチレーション(メチル化が不足している状態)」には、見過ごされやすいけれど心身にじわじわと影響を与える症状が多くあります。
低メチレーション(Undermethylation)とは?
メチル基(-CH₃)を十分に供給・活用できず、
神経伝達、エネルギー産生、解毒、遺伝子調節などに必要なスイッチが足りていない状態です。
低メチレーションに見られる主な症状
分野 症状の例
精神・感情 ✔ 気力が出ない/慢性的な無気力感✔ 鬱っぽい・悲観的になりやすい✔ 集中力の低下・記憶力の衰え
身体的な疲労 ✔ 朝起きられない/寝ても疲れが取れない✔ 冷え・低体温傾向✔ 筋力の回復が遅い
ホルモン・代謝 ✔ PMSや月経不順がある✔ 血糖の乱れ(空腹でイライラ、甘いもの欲)✔ 甲状腺機能が低めといわれたことがある
皮膚・髪・粘膜 ✔ 肌の乾燥や荒れ、アトピー傾向✔ 髪のパサつき・抜け毛が多い✔ 口内炎・口角炎が出やすい
解毒・腸内環境 ✔ においや化学物質に過敏✔ お酒や薬に弱い✔ 下痢と便秘を繰り返す
特に見落とされやすいサイン
• 「やる気が出ないのは性格のせいかも」と思っている
• サプリや健康法がうまく効かない
• 強い刺激(葉酸やB12)で気分が悪くなることがある
これらは、メチレーションが整っていないサインかもしれません。
原因として考えられる背景
• ビタミンB群(特に葉酸・B6・B12)の不足
• メチオニン・コリン・亜鉛などの材料不足
• 長期のストレスや副腎疲労
• 遺伝的にMTHFRなどの酵素が働きづらい体質
• 消化吸収力の低下(腸の弱り)
テロイドの副作用としてよく知られる「白内障」と「骨粗鬆症」について、発生のメカニズムと分子栄養学的な視点からの対策を以下にまとめました。
【ステロイドによる白内障の発生機序】
◆ 発症メカニズム
• ステロイドは水晶体のたんぱく質構造を変性させ、不透明化を引き起こすことで白内障を誘発。
• 酸化ストレス増大や、グルタチオンなどの抗酸化物質の枯渇も関係。
• 糖新生促進による高血糖傾向も、糖化ストレスを通じて水晶体への影響を与える。
【ステロイドによる骨粗鬆症の発生機序】
◆発症メカニズム
• ステロイドは骨芽細胞の機能を抑制し、破骨細胞の活性を促進することで骨吸収が優位に。
• 腸管からのカルシウム吸収抑制、腎臓からのカルシウム排泄促進が起こり、カルシウム不足に。
• ビタミンDの活性化を阻害し、骨代謝に悪影響。
🌿【分子栄養学的対策】
🟢 白内障への対策
- 抗酸化ビタミンの補給
• ビタミンC・E、グルタチオン
• これらは水晶体の酸化防御機構をサポートし、蛋白の変性を防ぐ - 硫黄化合物の摂取
• タウリン、システイン、メチオニン(抗酸化作用が強く、グルタチオンの材料にも) - 血糖バランスの調整
• 精製糖質の制限と共に、クロムやマグネシウムなどのミネラル補給も有効
🟢 骨粗鬆症への対策
- ビタミンDとKの補給
• ビタミンDはカルシウム吸収促進、Kは骨タンパク質の活性化に関与 - 良質なタンパク質とアミノ酸の摂取
• 特にリジン、アルギニン、グリシンは骨形成に寄与 - マグネシウム・亜鉛・ホウ素などのミネラル補給
• 骨のミネラルマトリックス形成や、ビタミンD代謝を助ける - 糖質の質と量の見直し
精製糖質過多はカルシウムの尿中排泄を促進
サプリメント摂取は体感だけに頼らず、量子共鳴磁気アナライザーや血液検査などキチンと測定して摂取する事をお勧めします✋

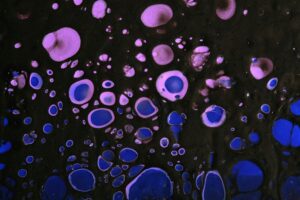



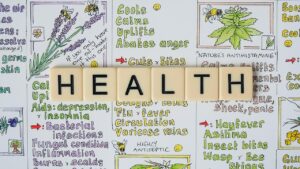



コメント